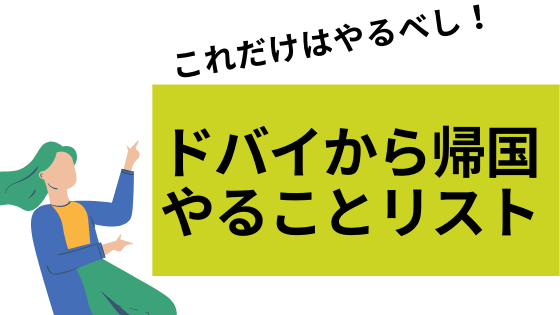あれよあれよという間に、この日を迎えた。
ドバイで最後の勤務日である。と言っても、引き継ぎは終わっているので、とりあえず会社にいますよ、という存在感だけを出しておく日々である。
本来ならば、最終出社日というのは、ワクワク楽しいものだろうが、どうも私にとっては、憂鬱である。
海外と日本では、最終出社日のお作法が、だいぶ異なるからだ。ドバイで数社働いたが、いつもこの日には憂鬱になる。
以前にも書いたが、とにかくハードルが高い。日本であれば、慎ましやかに、「どうも、ありがとうございました〜」と菓子折りを持って職場を歩くぐらいである。
が!
ここドバイでは、一人一人に、盛大なるお別れの祝辞を述べ、最後にグッとハグで締めるのである。大して関わりのないチームメンバーであっても、この抱擁をしなければならないという、暗黙のルールがある。
いや、ルールというより、ハグ文化がある人々の方が多いので、自然にそうなってしまうのである。
この一連の行為が、どうも苦手なのだ。
挨拶の時も、「今日で最後なんですよ〜、ありがとうございやした〜」という、静かなテンションは、断じてここでは許されない。
むしろ、「ヤホ!今日でうち、最後やねん。ホンマ、ありがとう。もう、さみしいわ〜!!」などと、ややテンション高めでいくのが好まれる。
正直に言えば、できれば誰にも気付かれずに退職したいと、思っていたので、最終日は身をひそめるようにして、退職時間を待っていた。
ポンポン
仕事中、いきなり肩を叩かれたかと思うと、そこに立っていたのは、数ヶ月前に会社を辞めていたヤスミンであった。
事情を聞くと、本日が最終日だと聞いて、わざわざ車で30分の場所にあるオフィスから、やってきたのだという。
私は、人望とはかけ離れた人間だと思っていたので、この突然のサプライズに驚いたものである。
ちなみに、このヤスミンは、かなりできる女である。デキすぎるがゆえに、こちらもおののいたことは何度かある。詳しくはこちら。
そんなんアリ!?仕事ができない面倒な上司に対する革命的な対応
彼女は、私が一緒に働いたアラブ人の中で、唯一尊敬ができて、一緒に働いてよかったな、と思える人であった。
この会社を辞めようと思ったのは、それほどポジティブな理由からではない。正直に言えば、社内の政治関係と新たなポンコツ上司のもとで、働くのに疲れたからである。
このまま放っておけば、精神汚染が始まり、以前のような廃人寸前になるだろう、と察知したのだ。
それでも、この会社で働けたのは、よかったと思っている。仕事としては、う〜んと思うことは多々あったが、50カ国以上の人々が働くオフィスは、自分にとっては刺激の連続であった。
言語力や内向的性格、文化的違いゆえに、理解されず、理解できず、葛藤を抱えることもあったが、彼らから学ぶことは、仕事以上にあった。それは役職や国に関わらずである。というか、関わった人の中で、学びを与えてくれなかった人などいない。
100人以上いるオフィスで、自分と同じ文化を持ち、言語を話す人はいない。すべての人が違うからこそ、常にそこには、日本では遭遇できないような、気づきがあった。
その点においては、すべての人々に感謝してもしきれない、と思っている。
こうして、のうのうとノープランで、ドバイをやめま〜す!と言えるのも、そうした人々の生き様に触れたせいもあるだろう。

チームメンバーとの一コマ。ソマリア、エジプト、モロッコ、パレスチナ、インドと年齢も国も境遇もみなバラバラの人々であった。
会社を去る間際、プレゼントをもらった。
ドバイでは、退職者が菓子折りを渡すという行為は、見られない。が、退職者がプレゼントをもらう、ということはある。
もらったのは、3冊の本とピカチューの寄せ書きだった。
ヤスミンがくれたのは、エジプトのガイドブックだった。私が中東のあちこちに行っているので、それを察してガイドブックを買ってくれたらしい。その心遣いには、感謝しかない。

もらった3冊の本と寄せ書き
私が所属するチームでは、メンバーの誕生日や誰かが辞めていく度に、寄せ書きを書いて渡すという、習慣が根付いていた。
そこで、私がメッセージの隣にピカチュウを書く(気分がのっている時は、カービィ)ので、チームの誰かが、私がピカチュウ好きと勘違いしたのかもしれない。
ピカチュウの上には「清和」の文字。私の漢字名など知る由もない同僚が、頑張って探してきてくれたのだろう。正解は「聖和」なので、ニアピン賞である。
ドバイで職を探し、仕事を始めるのは容易なことではない。けれども、辞めるのはこれほどあっさりしているのか、と思ったものである。
そんなわけで、晴れてドバイの最終出社日を終えたのであった。もっと、感慨深くなるかと思ったが、あっけない終わりであった。