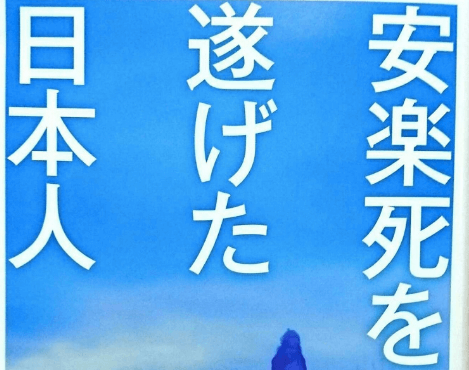安楽死。聞いたことはあるが、実際にはどこでどのように行われるのか、ということはあまり知られていない。
老老介護、自殺、介護疲れ、延命治療といった死にまつわるおどろおどろしいワードが蔓延する社会からすると、安楽死というのは、字面の通り楽に最後を迎える方法のように聞こえる。
私は、死ぬなら安楽死で死のうと数年前から決めている。
別に今、死にたいわけでもない。また、難病に侵されているわけではない。自分の死に際が間近に迫っている年齢でもない。まだ死を考えるには早すぎるであろう、30歳に満たない年齢である。
でも生きている以上、死について考えることは不可避である。死について考えることはタブー視されている。けれど、私としては真面目に生きているつもりなので、真面目に死についても考えておきたいのである。
人間長生きできれば、幸せなのか
今の時代、簡単に死ねやしない。医療が発達して、世界でも屈指の長寿国になった日本では、人間が80年や90年近く生きることが前提とされている。
人生100年時代などとも言われるようになった。長寿国の日本では、ごく当たり前のように人々はそれを受け入れ、100年をどう生きましょうかね、と前向きな議論がなされている。
けれども、私は思う。そもそも100年も生きる必要があるのか。寿命が延びることは本当に嬉しいことなのだろうか、と。
いくら肉体的に100年生きることができたとしても、それは私が考える「生」には程遠い。人間はしょせん自然である。食べ物と同じように賞味期限がある。歳をとれば、若い頃のようにアクティブに動いたり、食べたり、考えたりすることはできない。
よって、肉体が思う通りに動かず、自分が自分であるように思考ができれば、肉体的に生きていようが、私が思うにそれは生に値しない。
身体だけ100年生きたとしても、そこに自分を自分たらしめる思考や行動がともわなければ、それは死である。
「生」と「死」の境目はどこなのか?
このように考えるようになったのは、ささいなことがきっかけだ。大学生の頃。イスラエルに留学前に老後ホームでの1日ヘルパー体験を志願した。
介護やボランティアにとりわけ関心があったわけでない。むしろ、世界でも稀なる高齢社会の実態をこの目で見ておきたかったのである。
1日体験のほとんどのことは、もう忘れてしまったが、今でも脳裏に焼きついている映像がある。それは、施設に入っているお年寄りを入浴させるシーンだ。
ストレッチャーに乗せられた丸裸の男性が、広い浴室に運ばれてくる。男性はじっと横たわり、うんともすんともいわない。
ストレッチャーから、機械的に浴槽につけこまれ、入浴をすます。その後、ふたたびストレッチャーに乗せられ、職員たちがタオルで体をふき、仕上げにベビーパウダーを体中にはたきかける。
「こうやって、ベビーパウダーをつけると、床ずれしにくいのよ」
平然と私に話しかける職員。しかし、私は見慣れない光景に驚愕するばかりだった。
全然、ベビーじゃないのに!?
目の前には、微動だにしない赤の他人の裸体。あまりにも動かないので、本当に生きているのだろうか、と疑わしくなるほどである。
その体には無数のしわが余すことなく刻まれている。我々が一般的にイメージするハツラツとした肉体と同じものとは思えなかった。
それを複数人の職員たちがとりかこみ、ベビーパウダーをはたいている状態。こうした高齢者の入浴があまりにも手際よく、工場のベルトコンベヤーを流れる商品のごとくであった。
なんだこれは?
自分も将来、ベルトコンベヤーの商品のごとく、己の肉体を見知らぬ人にさらし、お風呂にいれてもらうことになるのだろうか。そして、そのことに羞恥さえ感じなくなるのだろうか。
目の前の男性は、肉体的には生きている。けれども、その「生き方」は私が思う「生き方」とは、ずいぶんとかけ離れていた。
祖母は2回死んだ
生きることと死について、ふたたび考えさせられたのが、祖母の死である。
日に日に弱っていく祖母の姿を定点的に見ていて、人は2度死ぬのだな、と思った。
その事故が起こるまでは、80歳後半でありながら、毎日の犬の散歩を欠かさず、意思明瞭で、俳句をたしなむ祖母であった。夫である私の祖父が先立ち、10年近くたつが、1人暮らしもそつなくこなしていた。
祖母は、俳句コンクールで数々の賞を受賞するほどの、腕前の持ち主だった。
あまりにも俳句熱心だったためか、そんなものには興味すら示さなかった母親までもが、なぜかインスパイアされて、俳句作りにいそしむようになったほどである。
しかし、犬の散歩中に転倒したことをきっかけに、病院生活が始まる。若者だったら、なんてことはない怪我であっても、80歳をすぎた高齢の体には、致命的だった。
祖母が入院する病院に、何度か訪れた。
けれども、そこには事故以前の祖母は、もういなかった。
ハキハキとした口調で、いつものように「よく来たねえ」と再会を喜ぶ祖母ではなかった。ただ、ぼんやりと焦点が合わず、ぶつぶつと何かを話している。ただ、柔和な祖母の姿は、そのまま残っていたことが、唯一の救いだった。
とてつもない喪失感に襲われた。
あれ・・・なんだか涙が止まらない。
この涙の分量は、人の死に直面した時にしか発生しないやつ、なんだけどな。
目の前に確かに、祖母はいる。けれども、長く慣れ親しんだ祖母は、もういなかった。
高齢の家族をもつ人々にとっては、当たり前の体験なのかもしれない。けれども、祖母をたらしめる何かが失われて、祖母の姿形しかその場にはない、という事実がとてもショッキングであった。
私が慣れ親しんだ祖母は死んだ。けれども、肉体としての祖母はまだ、いる。
日本人が安楽死をするのには
安楽死は日本では認められていない。世界でも安楽死が合法になっているのは、ベルギーやオランダ、アメリカの一部の州といったわずかな国だ。しかも、その多くの国では、安楽死が認められているのが自国民だけである。
一方で、スイスには外国人も受け入れている団体がある。それが「ライフ・サークル」。
年会費の50スイスフラン(約5,400円)を払って団体に加入することが可能だ(2019年8月現在では、新規メンバーの募集を停止中)。そして「安楽死を遂げるまで」の著者、宮下洋一氏によれば、安楽死にかかる費用は、診断書作成費やスイスへの渡航費などを含め、200万円ほどだという。
とはいえ誰もが安楽死できるわけではない。医師との面談や診断を経て、安楽死をする条件にあたるかどうか、を見極められる。以下は、同団体が掲げている安楽死の条件だ。
安楽死の条件
- 耐え難い苦痛がある
- 明確な意思表示ができる
- 回復の見込みがない
- 治療の代替手段がない
さらに、安楽死をするにあたって英語かドイツ語での基本的な会話力が必要になる。診断書も英語で用意しなければならないからだ。
正直に言えば、安楽死という選択肢は、ある意味で安心感を与えてくれるのも事実だ。
人生100年時代においては、いろんなことを考えねばならない。
年金、病気、保険、孤独死・・・不確定かつ長期戦になるであろう将来について、考えたり決めたりすることは多くある。
私は、正直こうしたことを考えるのが憂鬱だな、と思う。ましてや、海外に暮らしていて、年金も国民保険も払っていない身分である。今後、日本で暮らすかどうかもわからない。
しかし、極論を言えば、安楽死という選択をすれば、とりあえず200万円あれば死期を迎えることができる。200万円というのは、安楽死の実施費用に加え、スイスへの航空券、ホテル代、火葬代などを含めての金額である。
けれども、あることが不確定な未来に対して、「万が一の際には200万円もってスイスに行けばいい」という明確な選択肢が、一種の安心感を与えてくれるのも事実なのである。
安楽死を選んだ日本人
すでにスイスの団体を通じて安楽死を行った日本人女性もいる。NHKで放送された「彼女は安楽死を選んだ」は、難病の女性が安楽死を決意し、それを実行するまでを追ったドキュメンタリーである。
そこには、自らの命日を決め、安楽死死を遂行する、という見たこともない不思議な世界が広がっていた。
自分でいつ死ぬのかを決め、死ぬ前日に姉妹たちと文字通りの最後の晩餐。ひたすらお互いに「ありがとう。幸せだったよ」と述べ合う。
そして、このドキュメンタリーでは、実際に彼女の安楽死の瞬間すらとらえている。あまりにも穏やかなその死の瞬間は、大事な人に見守られ、ぽっくりと死ぬ、という多くの人々の理想を連想させた。
従来の死に方とは違う、まったく新しい死の形を見せられることで、まるでSFを見ているような気分にもなった。
けれども、そうした世界は本当に実在するのだ。
多くの国では合法化されていない。議論も多くある。批判もあるだろう。新しい価値観やあり方は、国の法も多くの人々もすぐに受け入れることはできない。
人間が意図せずとも長生きできてしまう社会。そこには、多様な「生」の定義や生きる目的がある。だからこそ、死に方も多様になる。
安楽死が実施できるということは、そうした多様な死に方に対して、選択肢が1つ増えたということを意味するのだろう。