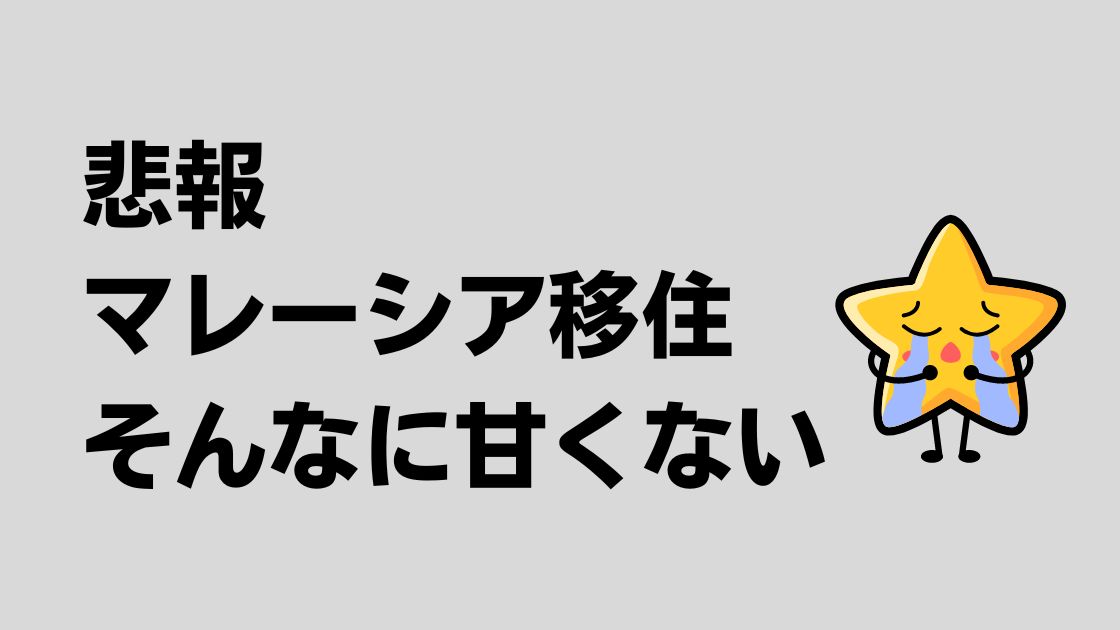マレーシアに住んで以来、毎朝ジャングルに行くことが日課となっている。私は密かにこれをジャン活と呼んでいる。
ジャングルといっても正式には、丘と呼ばれている。確かに高さ的には丘なのだが、「丘を越え〜行こうよ〜」みたいな牧歌的な丘とは似ても似つかない。鬱蒼とした木々が生い茂る、ジャンルグルのイメージそのものである。よって私は中立な立場からジャングルと呼んでいる。
ジャングルには、ニワトリ、ワンコ、蛇、リスなど各種生命体がそろっている。猿にも頻繁に出くわすので、定点観察を行なっているのだが、どうやらその猿の様子が最近変なのである。
かつては猿たちは、森の中で慎ましく木の実をたべていた。森の中で出くわしても、知らんぷりである。しかし最近では、森にエサがないのか民家の近くにまでやってきて、ゴミ箱や道路脇でエサをあさっている。
ただ民家近くにやってくるだけならいざしらず、凶暴性を伴っているのでタチが悪い。ある日、ジャングルに向かってきた時のこと。道路の真ん中に立つ10メートルほどある街頭の上に、一匹の猿がいた。
何をしているのかと見ていたら、わけもなく街灯を激しく揺さぶっている。威嚇なのかと思いきや、あたりには威嚇対象物もいない。気が触れているに違いない。まるでそこだけマグニチュード7の地震が発生しているかのごとく、電灯だけがわさわさと揺れているのである。
またある時には、あまりにも飯に困ったのか、いつもはハト軍団がたまって、穏やかに食事をしていることころを猿軍団が襲撃。ハトから飯を強奪していた。まるでチンピラである。
ハトたちも手の施しようがなく、安全な土手に避難し、チンピラの襲撃を見守る他ない。
そして事件はついに起こった。
ある朝、車の往来が激しい道路に、猿集団がいたのでしげしげと眺めていた。
ははあ、猿も大変なんだなあ・・・
と猿たちを見ていた瞬間。
ボスザルと思われる体格のいい猿が、歯を剥き出しにして「キエーーー」と、こちらへ突撃してくるではないか。ヤマンバばりの迫力である。
ぎゃっ
と思うヒマもなく、身体はすでに猿から逃れるために全力疾走を始めていた。しかし、こともあろうに私の身体がチョイスした逃走経路はかなりの坂道である。
しかし、そんなことには構っていられない。攻撃されたら終わりだ。
人間は走ることができる。
しかし、本能で走ることなど人生で何回あるのだろうか。
今、私は本能で走っている。
小学校の50メートル走や趣味のお気楽なランニングではない。
心の底から生死をかけて走っているのだ。
猿はしぶとい。坂を20メートルぐらい全力疾走しているのに、まだ猿の息遣いが背後にあるのが分かる。
くっそ。どんだけ追いかけてくるんや
50メートルほど走ったところで、人の往来がある場所へ出た。背後を振り返り、猿がいないのを確認。ようやく追手から逃れることができたらしい。するとそこへ、
「きみい〜猿に追いかけられてたね。めちゃくちゃ早かったよ☆ナイスラン!」
とジモティーランナーが後ろから声をかけてきた。
のんきな発言である。
猿からの決死の逃走を目撃されていた、という恥ずかしさと、助かったという安堵の複雑な気持ちである。
動物と目を合わせることは、敵対行為であることを後に知った。故に、私が猿を見ていたという行為が、この逃走劇の発端となったのだ。
それにしても、である。私は自然を甘く見ていたらしい。都市生活がメインとなっている人間にとっては、自然や動物は癒しと言われることがある。しかし、今回の件を経て、癒しというのは人間の勝手な見方に過ぎず、自然は脅威だと思った。
自然は人間のルールの計り知れない、営みである。だからこそ、そのルールや前提が通じない自然や野生動物は人間にとっては恐怖でもあり、時には畏敬の対象にもなるのだ。