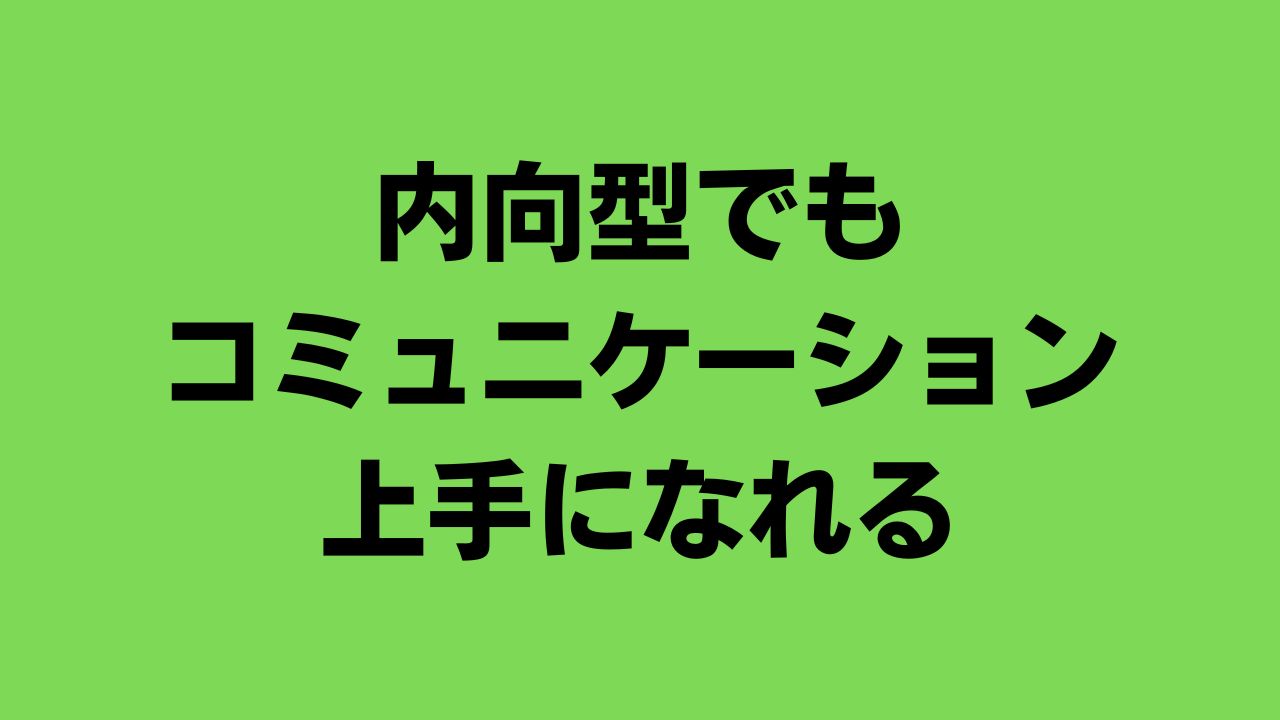メールが届いた。差出人を見ても見覚えがないので、スパムメールだろうと思った。しかし、開けてみるとメールは長文で、イスラーム美術講座でクラスメイトだった人物からだという。文章を何度か読み返したものの、やはりその名前から顔が思い出せない。過去のメールのやり取りをみると確かに、彼女とやり取りをした記憶はあるが、それ以上のものは出てこない。
メールには、私が最近ベルリンに移住したことを知ったこと、自分は今ドイツのニュルンベルク近くの小さな町に住んでいるが、1ヶ月後に上海に引っ越すので、その前に会いたいということ、そして2年前から定期的に私のブログを読んでおり、その生活スタイルに憧れを抱いていた、ということが書かれていた。彼女は日本語を話さないので、自動翻訳を使ってまで私のブログを読んでいたことに驚いた。
メールの長文からうかがえる熱心さに負けて、私は顔も知らぬ彼女に会いに行くことにした。ちょっとしたミステリーツアー気分である。しかしベルリンからたった3時間の場所だというのに、チケット代がめちゃくちゃ高いこと、そして遅延するのがデフォルトというドイツの鉄道に乗るのは、気が重く感じられた。しかし、それでもミステリー感漂うこの出会いへの期待が勝り、会いに行くことにした。
駅に到着する前に、彼女が自分の顔写真を送ってくれた。これをみて、私の不安は一気に安堵へと変わった。どうやら私は、別のクラスメイトを想像していたらしい。心配していた電車も、時間通りに着いた。
小さな駅の改札口を抜け、町へ出るとそこは本場ドイツだった。ドイツの首都ベルリンから来たくせに何をいっているのかと思われるかも知れない。しかし、その小さな町には、路上にゴミや空き瓶がなく、ゴミ箱をのぞいている人もいない。ホームレスもおらず、小汚い人もいない。これらがベルリンのデフォルトの光景である。思わず路上の空き瓶をキョロキョロと探してしまう私。
ベルリンでは、空き瓶を集めるとお金に換金できるので、ホームレスの人のために、わざと路上に空き瓶を放置している。なので、路上の空き瓶はポイ捨てではなく、優しさの置き土産なのである。
久しぶりというか初めての対面だったが、我々は一瞬で意気投合した。彼女のおすすめだというホットココアをカフェで注文し、町を練り歩く。彼女の住む町は、本当に小さくて20分もすれば、町を一周できるような規模だった。
私は誰かから尊敬されたいとか、誰かの生き方に憧れるといった心を持たず、ただひたすら自分の生を生きてきたのみなのだが、彼女にとっては「自由に生きる憧れのライフスタイル実践者」として私は映っていたらしい。しかし、彼女もまた母国のパキスタンを離れ、スペインやイギリスを含めヨーロッパに8年間滞在しているので、私は「おたくも相当すごいじゃないか」、と言った。私のライフスタイルに憧れる理由がどこにあるというのか。
その後、彼女の家に泊まらせてもらうことにした。片道3時間もかかる上、予定通りに電車がやってくるとは限らないため、流石に日帰りはきつい。それに、急いで帰るほどの用事もベルリンにはない。
彼女が住む家は、5階建ての比較的新しく綺麗なアパートで、各階の玄関の外には、住人の置物や靴が置いてあり、ベルリンでは考えられない治安の良さに衝撃を受けた。ベルリンだったら1日もしないうちに、盗まれている。ルームメイトである家主のドイツ人婆さんは、南の島にバケーションに行っており、2週間ぐらいは戻らないという。彼女もまた上海への転勤が決まり、この1ヶ月は仕事もなく、ただ次への準備期間として過ごすそうで、私はそこに今の私が抱える寂しさや焦燥感が充満していることを感じ取ったと同時に、彼女が私を呼び寄せた理由も明らかだった。
外は雪が降り積もり、中心地から離れた彼女が住むエリアは、ただ家々が集合しているだけなので、外に出てもやることはない。自動的に我々は家の中にこもることになった。彼女があらかじめ作ってくれたプラオをランチとしていただき、その後、ただひたすら話し続けるのもなんなので、手持ち無沙汰な身体を使ってりんごケーキを焼いた。身体が動いていれば、なんだって良かったのである。
外で料理をする場合、料理教室などスキルアップや仲間作りを目的としていることが大半である。料理は友達と一緒に行うアクティビティではない、というのがそれまでだった。けれども、これだけ天気が悪いと家に籠るしかなく、また日曜日に至ってはドイツではほとんどの店が閉まるので、意外とありがちなアクティビティなのだという。
我々は共にシングル。彼女は私よりもちょっと年上で、私は彼女が単にシングルであるということよりも、ムスリムである彼女が恋愛にどのような思いを抱いているのかが純粋に気になった。
彼女の口から発せられる恋バナは、総括すると半透明な色とりどりの飴の集合体だった。見た目の美しさからはその純粋さがうかがいしれるが、口に入れるとすぐになくなってしまうほどはかない。噛めば噛むほど旨味が出るガムとは違う。ただ飴は、長年放置していても、その色が褪せることはない。そうした鮮明な色を彼女の恋は、いまだに放っていた。ただ、彼女がしきりに、「ポークを食べる人は嫌、口が不潔だからキスなんかしたくない」と、豚肉を食べるメンズを汚物扱いしていたのには、笑えた。
外は薄暗く、家という狭い空間で、ウマの合う2人が会話を展開すると、話はどんどんディープになる。それが、明るい日中のカフェだったら?陽気な話に終始していたかも知れない。ドイツの寒さと暗さに気分が滅入っていた私だが、ある時になって寒さと暗さこそが、内なる対話をするには絶好の環境だと思うようになった。太陽がサンサンと照る場所では、感じえない感性や言葉が、暗く寒い環境の中では、1つずつ丁寧に受け止められる。これはドイツが歴史的に有名な思想家を多く輩出してきたことにも関係しているのかもしれない。
多国籍な人間が暮らすドバイに住んでいた時、「結局、人間って同じ国の人間と、つるみがちなのかもね」というと、シリア難民の同僚がこういった。「人間のウマが合う合わないは、同じ国籍だからというもんじゃない。国が違っても、経済や家庭環境が同じであれば、生活レベルや思考が似てくるから、そっちの方が人間同士をくっつける強力な要素になるんだ」と。私と彼女はその例だったのかもしれない。
彼女がドイツを去る理由は、私がドイツに来た理由と同じであった。「上海/ベルリンで新たな生活をしたい」。目的地こそ違えど、ミッションは同じである。彼女は長年いたドイツやヨーロッパの生活に飽きを感じ、新天地である上海を目指すのだ。ドイツを去る理由について、彼女はこういった。
「言葉を流暢に話せても、どれだけ社会に馴染もうと努力しても、この国は私のような移民を本当の意味では受け入れてくれないの。そうした社会に対して、しがみつくことに疲れちゃったわけ。だからもういいの」
まだドイツ社会に足を踏み入れた私には、正直ピンとこなかった。それでも、過去の経験から、おそらく私もまたこの轍を踏むことになるだろうということは、予測できた。私はドイツ新参者。そして彼女はドイツを去る者である。こうしたすれ違いはどこにいても起こる。けれども我々は決まってこう約束する。
「また世界のどこかで会おう」
記念に2人で写真を撮ろうと言った。自分から写真を撮ることなど滅多にない私にしては珍しい。パキスタンにいる元クラスメイトたちに、2人の感動の再会を知らせたい、と言ったのだが、彼女は頑なに拒んだ。
「彼らは私にとってもう過去の人達だから」
それを言えば、私だって過去の人ではないか、と聞くと、「あなたは今ドイツにいるし、私もドイツにいる。何より、一度会ってみたい憧れの存在だったから」。彼女の頑な姿勢に引っ掛かるものがあったが、偶然の巡り合わせこそが、人を引き合わせるのだろうと良い方向に解釈することにした。逆に言えば同じ人間であっても、タイミングが少しずれれば、会うことはない。まるで数百年の間に起こるか起こらないかといった、宇宙の不思議な現象のように。だからこそ、そうした出会いは一瞬の出来事であれ、とても美しい光を放つ。
彼女との出会いは、単なる一瞬の楽しいひと時では終わらなかった。8時間ぶっ続けて話すことで、通常ではたどりつくはずのない場所にまで、流れ着いてしまったのである。
それは一人の人間との関係性が永遠に断ち切られた瞬間だった。糸が切れるようなあっけなさと、耐震偽装問題のように、それまで堅牢だと思われていたものが、実は虚しい脆弱なものだったと知った時の呆然。やりきれなさから酒を煽ることにした。しかしムスリムの彼女は酒を飲まないので、酒がない。小さな住宅地には深夜まで開いているコンビニもない。ビール大国ドイツにて、アルコールが手に入らないという、絶望。
酒がないとわめくのも大人気ない、という気持ちと酒をどうしても飲まねばやってられんという欲望で揺れながら、だんまりを決め込む私を見かねて、彼女は冷蔵庫から1本のビールを発掘してきた。ルームメイトの婆さんのビールだという。「勝手に婆さんのものを飲むのは気が引ける」という彼女に対し、「同じものを買って元に戻せば大丈夫」と言い聞かせ、私は強奪したビールを一気に飲み干した。しかし残念ながら、さほどの効果はなかった。ようやく眠りについたのは、明け方だった。それまでは、居間にあるベッド代わりのソファとトイレをひたすら往復していた。ただ残ったのは、疲労と翌日同じ銘柄のビールを買いに行かねばならぬ、という責務だった。
その日以降、私のドイツ生活は一変したものになり、殺虫剤を吹きかけられた瀕死寸前の蝿のように、のたうち回ることになったのだが、今ではあれが受難と救済の始まりだったのだとすら思える。もし彼女に会わずに、ずっとあのままの生活を送っていたら・・・と思うと、ゾッとする。彼女が私に会うことを望んだのではなく、私が彼女を必要としていたのだろうすら思う。
おそらく今、彼女は上海行きのフライトに乗っているはずだ。そして私の家には、彼女から譲り受けたイスラーム美術の分厚いコーヒーテーブルブックが置いてある。