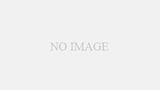とある人がこんなことを言っていた。
「ベルリンにはあらゆる価値観がある」
最初にそれを聞いた時は、無知ゆえに、「へえ〜」と適当に流していたが、それが今とても腑に落ちている。そしてそんな多様性に私はひどく打ちのめされることになる。
Timeleftというアプリを使って、見知らぬ他人が勝手にマッチングされ、ディナーを共にするというサービスを使ってみた。食事会には6人が集まる予定だったが、結局やってきたのは4人。時間通りに来たのは、2人だけというスロースタート。
先に来ていたのは2人の男性で、セントビンセント(私はこの時初めてそんな国があることを知った)出身だが、デンマーク育ちというおしゃべりマッチョ。「俺、2つもコミュニティを運営しててさ〜、今はスタートアップでAI関連の仕事をしてるんだ。1日12時間も働いてさ・・・」などと、聞いてもいないのに、忙しいアピールをしてくる。
もう1人は、ブラジル出身でポルトガル国籍の方。おとなしい感じで、しかも3年間日本語を勉強(アニメに触発されたわけではない)していたという。2人ともベルリンには4年以上住んでいるので、一応パイセンと呼ぶことにする。
遅れてきてやってきたのが、フランス国籍を申請中のコロンビア人で、こいつがとんでもないダークホースであった。「俺みたいなノマド生活してるとさ、話が合う人を見つけるのが難しくて。よくChatGPTと会話してるんだ」などと、ChatGPTを”it”ではなく”she”と呼んで、単なるテクノロジーに性別をつけている奇人だった。さすがのおしゃべりマッチョも明らかに引いていた。
見知らぬ他人同士が集まるということで、運営者側も気を遣ってか、アプリ上で「ゲーム」を提供している。アプリ上に、次々と質問が提示され、それに答えていくというものなのだが、「子供の頃の恥ずかしい思い出は?」だとか「冷蔵庫に必ず入っているものは?」など、正直いってどうでもいい質問である。よって我々はすぐにゲームをスルーし、フリートークに移っていった。
マッチングアプリの話をしていたところ、マッチョがこんなことを言い出した。
「俺、パートナーが3人いるんだよねえ」
ひえっ!?
と驚いているのは私だけである。他の2人はそれが当たり前のように受け流し、「へーそれで?」などと、のんきに話を続けている。「どこでそんなパートナーを見つけたんだ?」というのが、コロンビア人の最大関心事項であった。そっちかい。
あれ、過剰反応する私がおかしいのかしらん。私だけ一人、世にも奇妙な世界に入り込んだような気がした。一人動揺していると、ブラジルのパイセンが「ベルリンではよくある話だよ。ベルリンはとてもリベラルな場所なんだ」と穏やかな笑顔で解説する。
伝統的な社会であれば、「浮気」や「不倫」になることも、多様性の社会ではそれが名前を持ち、1つのあり方として認められる。一方の社会では3股と呼ばれ非難されても、ノンモノガミー(2人以上の相手と関係を持つこと。モノガミーは一夫一妻制)とさえ名乗ってしまえば、無罪放免である。それを責めたり、避難することは、リベラルな社会では、「いやあねえ」などと”遅れた”人間として無言の非難を浴びる。
「3人もパートナーを持つ必要があるの?1人でよくね?」
「別に複数のパートナーを持ちたかったわけじゃないんだ。気づいたら3人になってただけ」
なんだその一休さんのトンチみたいな答えは。
「それはいわゆるセフレなんじゃ?」
「1人1人の関係が違うんだよ。パートナーAとはこれをして、パートナーBとはあれをやって。必ずしもセックスするわけでもないし。ただし、この関係を維持するのは、ガチで危険だし、ムズイ。相当な努力が必要なんだ。俺のパートナー同士でも了承が必要だし、とにかくコミュニケーションが大事。それに俺のパートナーである女性同士でも関係はあるからね」
は?
セカンドインパクト襲来。
つまりはマッチョが付き合っている女性3人もそれぞれ、繋がっているということなのだ。そして彼女たちもまた、彼とは別の男性と付き合っているのである。そしてマッチョもそれを許容している。
ネズミ講か。
「つまりは、彼女たちはみんなバイセクシュアルで、オープンリレーションシップってこと?」
「そういうことだね」
私は上海の友人の言葉を思い出した。
「最高のパートナーっていうのはね、すべてを満たしてくれる人なの。尊敬ができて、自分が成長できて、いつまでも飽きずに話ができて、女性としての自分を肉体的にも満たしてくれるの」
そう。マッチョがやっていることは、ある世界では1人に集約させなければいけないものを、3分割しているだけなのである。ただ、その3人を維持する労力を考えたら、1人の方が楽なのではないかと思う。1日12時間も働き、コミュニティにも定期的に顔を出している人間のどこにそんな時間があるのだろう。暇なのか?
狂ってる・・・
それが真に多様な社会に抱いた第一印象だった。しかしほどなくして、同様の事例を次々と耳にすることになる。
「昔ポリアモリーな関係を持っていたことがあるんだけど、あれはマジで大変。バイセクシュアルの女性2人と付き合ってたけど、女性2人の仲が悪くなってさあ。どっちを選ぶわけにもいかないから、結局2人とも別れたんだよね」という男性。彼はその後、一夫一妻の結婚を経て離婚し、現在に至る。
「1人の夫と結婚していましたが離婚し、最近は2人の男性と付き合っていて、どう2人と関係を続けていったらいいのか悩んでいます」という、Facebookに寄せられたベルリン在住者からの匿名の投稿。モノガミーからノンモノガミーに転身した女性らしい。複数人と付き合うことに疑問やためらいはなく、あくまで複数人とどう関係を続けていくかが、彼女の大いなる悩みらしい。
ここから分かったのは、ベルリンの息がかかると、モノガミーや異性愛者であっても、ノンモノガミーやLGBTQへの突然変異が起こってしまうらしい。あな恐ろしや。
私がその投稿以上に驚いたのが、誰も複数人と付き合うことに対して、非難することもなく、淡々と「そういう場合はね・・・」と悩みに対する真摯なコメントが多数寄せていることだった。
何だこの異様な空気感は・・・
これでは、今まで当然だと思っていた一対一の異性愛者との恋愛も、難しくなる。相手が異性愛者でも、モノガミー派かノンモノガミー派かをまずは確認する。バイセクシュアルかも一応確認。今はそうでなくても、過去にそういう経験があるのかも確認。複数のステップを経て、ようやく恋愛に入れるかどうかが決まる。
このように考えると、男女に対する見方がずいぶんと変わる。夫と妻の2人に見えても、実はもう1人の妻ないしは夫がいるかもしれない。男女仲良しグループに見えても、実は全員お互いに関係性を持っているのかもしれない、というように。少女漫画のように、2人の男女が出会って恋愛が始まるといった単純なプロットはもう描けない。
「同僚の男性がさあ、2人の女性と付き合ってて、子供を養子で引き取って、3人で暮らしていこうっていう話をしてるんだよねー」
ひいいい。親が3人という新発想。
狂いすぎてる・・・
私が出会う人がおかしいのだろうか。それとも、ベルリンがそうした変な輩を引き寄せるブラックホール的な磁場を持っているのだろうか。私はひどく混乱した。そうした人々が少数であれば、「へえー面白いね」と彼らをマイノリティ扱いして、マジョリティという安心した場所から、それを眺めることができる。しかし、何やらそうした人々がマイノリティではない、と気づいた時。自分の価値観がおかしいのだろうか、という自分への疑念が生まれる。それは、自分が今まで正しいと信じていたものが、瓦解するような恐ろしさでもある。
私って間違ってるのかしらん・・・
この”多様性”を受け止められない自分は、古くさい、遅れた人間なのだろうか・・・
みんなが、こんなに自由放題やっているのは狂ってる!嫌だ!
かくして私は錯乱状況に陥り、自分が何者なのか分からなくなった。当時の私にとって、こうしたあまりにも”自由”で”多様”なあり方は、脅威でしかなかった。それは生理的嫌悪につながった。ノンモノガミー嫌悪というより、それを受け入れきれない自分への嫌悪。そして自分が受け入れられない価値観が、当たり前にのさばっていることへの嫉妬と恐怖による嫌悪。
夫や妻ではなくパートナーと呼び、男らしさ、女らしさを押し付けない、ありのままの自分を認めましょう。これは多様性のほんの入り口であって、さらにトンネルを奥まで進むとさらにとんでもない化け物が待ち構えていた。私が対峙しているのは、ラスボスとも言える多様性のモンスターなのだ。
流石にこれらを多様性と呼んで、しかも礼賛するのはやり過ぎじゃないか。これが本当の多様性なら、私は多様性なんかいらない。
「昨今、マイノリティへの異常すぎる忖度によって、マジョリティが窮屈な世の中になっていた」
トランプ大統領がトランスジェンダー女子競技参加を禁止したニュース動画についていた、コメントである。まさしく私が感じていることであった。マジョリティへの脅威。多数派だと思っていた自分が、そうでなくなるという恐ろしさ。多数派にいれば、自分の価値観は正しく、自分を肯定できる。なぜなら多くの人がそう思っているんだもの。けれども、多数派でなくなるということは、常に自分の考えに対して、疑心暗鬼になり、差別や非難を恐れる。その感情は、かつて懇ろににしていたLGBTQの仲間達が抱えていたものだった。トランプのやっていることを支持するわけではないが、私はただベルリンで繰り広げられる”真”の多様性が怖く、一人怯えていた。
──1年前、インドネシアにある離島のジャングルにて。
裸族たちが未だ現役で原始生活を送るジャングル。ベルリンからやってきた男に出会った。彼は、「ベルリンで真っ当な人間として見られるには、最低でもバイセクシュアルじゃないとだめなんだ。異性愛者はクールじゃない」と言っていた。私はそんな摩訶不思議な場所があるのか、と好奇心をそそられた。当時の私にとってベルリンは、ラピュタの城のような存在だった。
けれども、今本当にラピュタは存在するのだと知った。そしてモノガミー兼異性愛者としてベルリンで生きる男の苦悩が、そのまま私の苦悩と違和感となっていた。
それから数週間後。
今だ多様性に対する最終的な答えは出ていない。けれども、あの怯えの現象は、アンチ多様性というよりも、新たな価値観にぶつかった時の衝撃から生まれるカルチャーショック期にいたのだと思う。それは今まで何ら疑いの余地がなかった、自分の価値観を再考する機会でもあった。中東という”保守”的な地域に10年近く住み、”結婚”という制度が未だメジャーとして残る日本出身の自分。これまで対岸で見ていた多様性の島に渡り、遠くで見ていた多様性と直近で見る多様性に大きな違いがあるということを知った。
今では、女2人、男1人という親のあり方に対しても、「狂ってる」以外の視点を持つことができている。「シングルはかわいそう?ならば2人よりも3人親の方が経済的にはよくね?というか、一夫多妻の国も世界にはたくさんあるわけで。それに哺乳類のほとんどは一夫多妻じゃん」と言ったように。これは、カルチャーショック期を経ての適応である。これについては、また別の機会に書こうと思う。