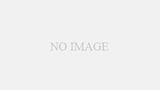嬉しいことがあった。朝起きると、すでに空が明るくなっている。これは何事か!と思い、時計を見やると朝の7時半。それまでは朝の8時を過ぎると、ようやく空がほのかに明るくなる程度だった。もちろん、南国のように大地をサンサンと陽気に照らすものではない。ベールのような薄暗い明るさが、窓から見えるだけだ。
たった30分。
30分だけ日の出が早くなっただけの話だ。ほんの些細なことなのに、なぜか圧倒的な勝利を掴んだような気がしてくるのはなぜだろう。事実私はガッツポーズをしていた。
もうすぐこの辛い冬が終わるのだ。
もうすぐこの戦争が終わるのかもしれない。絶望の中に見出したかすかな希望。それが、私にとってのたった30分間の早い日の出であった。本当に、この冬は終わるのだ。
日の出が早くなれば、日没もまた遅くなる。平日は毎日ドイツ語の学校に通い、授業が終わるのは午後4時。それまでは下校時と同時に日没が始まった。家に着く頃には、すっかり日が暮れている。その後外出すれば、まるで歌舞伎町の住人のごとく、夜遊びをしているかのような感覚に襲われる。
しかし、この頃はどうだろう。家までもうすぐのところに来ても、まだ空はほんのりと明るい。こんなに嬉しいことがあるだろうか。学校帰りに、寄り道をしてもまだ空は明るい。なんだかボーナスタイムのようで、妙に得をした気分になる。
それは、町の人々も同じだった。
家の近くにある立派な橋を渡ると、物珍しいものを撮るように、空に携帯をかざしている女性がいた。そこに何ら特別な被写体はない。ただ、青い空が広がっているだけだ。その横では、男性2人組が、立派なカメラと共に写真撮影をしている。いつもは暗闇の中、家路へと急ぐ人しかいなかったというのに。これを持ってして、日照時間が1時間伸びたことに、浮かれている人は私1人ではないのだということを知った。みな、これを待っていたのだ。
これまでほぼ10年間、冬がない国で暮らしてきた人間にとって、ドイツの冬はあまりにも厳しかった。尋常を保っていられない。体もおかしくなる。ちなみにクラスメイトが次々に、ドイツでの初めての冬に打撃をくらう中、ソウル出身のクラスメイトだけは、ただ一人何もくらっていなかった。ただ寒く暗闇の中にいると、常識ではわかっているが、まるでその終わりが見えない。精神的にも肉体的にも出口のない暗闇を彷徨うばかりである。
葉を削ぎ落として骨格だけになった寒々しい木々の中に、ただ一人爛々と花を咲かせている木が、家の最寄駅のそばにある。植物には詳しくない素人の見立てにより、季節外れの桜ということにしておこう。無知は時に幸福だ。雪が降る日も、風の強い日も、ただそいつだけは、淡々と花を咲かせていた。それはクリスマスマーケットが閉店したベルリンの冬における数少ない美しい風物であり、同時にちょっとした心の支えでもあった。あいつも頑張って花を咲かせているのだから、私も頑張ろうと。春は必ず来るのだ。生物たちが一斉に浮かれる夏に至っては、1本の木など目にも止まらぬだろう。さらには、1本の木を心の拠り所とするなんて、尋常ではない。
ベルリンからの逃避行と称して上海へ行った。乗り継ぎ地であるフランクフルトから上海行きの便は幸福だった。地上は曇天で激しい雪が降っているというのに、高く高く上空へ上がると景色は一変。雲ひとつない。日光が機内全体を満たし、思わず額に汗をかきそうになった。あれは単なる移動ではなく、至福の時間だった。地上の人間が、太陽に近づきうる最短の距離で浴びる日光。冷えた足先が温められ、鋭い光線が漏れなく体の細胞に入り込んでいく感覚。まるで羊膜に包まれた赤子のように、太陽に偉大なる母の優しさと原始的な喜びを感じるのであった。
そう。暗い冬は、太陽と私の関係を劇的に変化させた。日光はフリー素材ではなく、買うものになった。自然な愛が手に入らないなら、金で買ってしまえ、という発想と同じである。日の出が30分伸びたとて、どうしてもやりきれない寒さに参ることがある。春になりますよ、と見せかけての突然の寒波。そんな時は、日サロに行き、無機質なカプセルに閉じこもる。強めの日光20分を18ユーロ(約3,000円)で購入。目を閉じると、上海行きの壮大な日光浴のことを思い出す。しかし、目を開けると、怪しげなネオンが頭上を照らしており、ああしょせんは金で買った愛か、とリアルな現実に直面することになる。
この冬はいろんなことがあった。
11月からの冬の始まりにおいてはただ、冬への不平不満に徹するのみ。後半の1月以降にもなると、精神が海底にまでたどりついた結果、深海という新たな景色を発見した。ベルリンの人曰く、「冬は寒すぎるので、家に引きこもりがち」と言っていた。冬の人類はベルリンに限らずそんなもんだと思うが、私も例に漏れず、寒すぎて家に引きこもるようになった。新天地にやってきてまだ数ヶ月。安定したつながりや所属もない中で家にこもると、邪悪な孤独の妖精に囲まれ、蹂躙されかけたこともあった。
しかし、自分なりにもがくうちに、他人と繋がるのではなく、自分と繋がるというすべを覚えた。簡単に言えば、自分の趣味に没頭することである。私の場合は、お気に入りの小説家の本を読むことだった。日本語の古いの小説である。この頃は、カルチャーショック期にもあったため、自分の出自への愛着が一層増す。ささやかな原点回帰運動だ。要は、日本語という”分かる”世界に没入することで、”わからない世界”とそれに”苦悩する自分”を緩和するモルヒネ的な役目を果たす。こうした一種の文化的”ひきこもり”に見える行為が、その後新たなカルチャーへの拒絶になるか受容に向かうかは、当人の勇気と力量次第で変わってくる。
そうこうするうちに、他人や社会との関係性から生まれる孤独の妖精は消え去っていた。そして、自分と深く繋がることによって、自分の新たな一面にも出会うことになった。もちろん、他人と繋がることが効果がないというわけではない。当時は、実はこれまで以上に人と繋がっていた。ただ、人とのつながりの中に孤独の解消を見出すことはできなかった。根本的な解消は、自分自身が満たされている状態を作ることなのである。
いつも太陽がそばにいた時代。私は私の知るすべてが、私なのだと思っていた。しかし、暗闇の中で徘徊していると、自分という家の中に、見たことも入ったこともない地下室があることを発見した。そこには、見慣れぬ感性たちが、亡霊のように徘徊していた。肩を叩いて話してみると、意外に話が盛り上がる。面白い奴じゃないか。明るい心地の良い場所では、ただひたすら家の外に出て遊びに呆け、地下室の存在など知る由もなかっただろう。この地下室の発見により、私は暗くて寒い冬も悪くはないな、と思うようになった。夏になれば、この地下室への階段はきっと閉ざされてしまうことだろう。
冬と居心地の良い関係性を築き始めた頃、別れの時がやってきた。最初は嫌なやつだと思っていたけど、意外にも仲良くなっちゃって。そんな奴が来月いっぱいで転校する・・・そんな気分である。
本当は待望の春がやってきて嬉しいはずなのに、少し寂しい気持ちがする。けれども、今ではなぜか自分が誇らしい。この厳しい冬を乗り越えたのだ、という自信がどこからもなく湧いてくる。春を前に、私は冬季修了証明書なるものを、どこからともなく授与されるような気がしてならない。