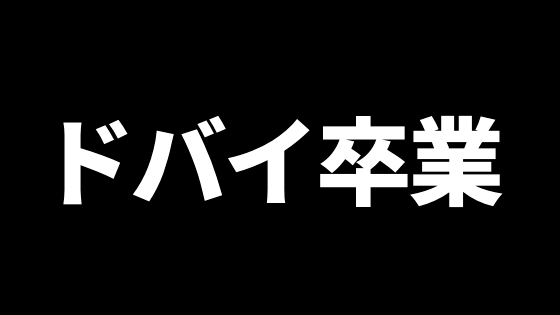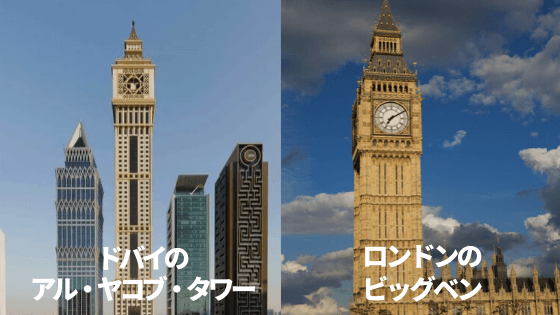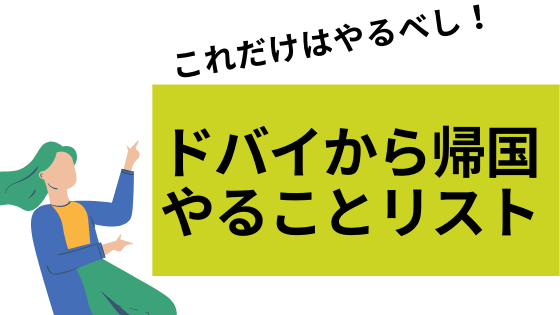あと数時間でドバイから、おさらばである。
ドバイ離脱を決意してからは、「これで最後なんだな・・・」といろんなところで、感傷にふけるようになった。
通勤路の光景。家のベランダから見えるモスク。ドバイの太陽とポッカポッカ陽気に浮かれて、道をきゃっきゃしながら歩くロシア人観光客。頻出キャラのインド人やフィリピーノたち。12月なのに汗ばむ気候。
まあ、最後となると、普段は何気ないものでも、手放したくないような、愛おしい気持ちになるのである。
人口の8割が外国人というドバイ。UAEに貢献した立派な市民には、永住権あげましょ、という動きはあるものの、ほとんどの人は、いずれはドバイを去るのである。
いつかは来るだろうと思っていたが、実際にその日が来てしまうと、やはり寂しくなる。
それは、大学や高校の卒業と似ている。確か、大学に通ったのも同じぐらいの期間だった。
そんなわけで、ドバイを去る前の数日間は、何かを見つめては、放心状態のごとく、ぼうっとすることが多かった。すべてが最後なのである。
この部屋で目覚めるのもこれが最後。通いなれたスーパーで買い物をするのも最後。近所のミニマートの店員と話すのも最後。
私が去ったあとも、こうした光景は、えんえんと続いていくんだろう。そう、考えると、さらに寂しさが加速する。
少しずつモノがなくなっていく部屋を見る度に、過去の思い出が募っていく。
そんなことを考えながら、ドバイでの残り数時間を噛みしめる。
ブブブ
Whatsapp(LINEみたいなもん)に、メッセージが入った。
「すまんすまん。今週忙しくてさ〜。ようやく時間ができたけん。今から、ご飯でも食べにいかん?」
ひえっ!?
こちとら、数時間後には、空港にいなきゃあかんのやぞ。
そんな暇は・・・
ないことはない。
能天気なメッセージをよこした主は、会社の同僚であった。一応、帰国日は伝えておいたつもりだったのだが、深夜便だとは思わなかったらしい。
そんなわけで、ゆっくりと最後の数時間を過ごす予定だったが、数十分後に落ち合うことにした。
返信した瞬間から、1秒も無駄にしない動きで、荷物を整え、入浴を済ませ、部屋のチェックアウトのため、ホテルの受付に向かう。もはや自衛隊である。
「あれ〜、お客さん。日本の人?そんなに荷物持ってるってことは、日本に帰るの?」
チェックアウト中、受付の青年が声をかけてきた。
顔面には、つながった眉毛。独特のセンスを見せつける男だ。ウズベキスタンからドバイにやってきて数年だという。
よくよく聞くと、彼の親戚が何人か日本に住んでおり、そのうちの1人が、パン屋を営んでいるという。日本風のパン屋ではなく、ウズベキスタンのパンを提供する店だという。
世界というのは、どうも狭いらしい。
気が向いたら、パン屋で働く親戚に言付けといたるわ、ということになった。そんなことをしているうちに、能天気な主が現れた。
元自宅から、歩いて2分ほどの場所にあるホテルのラウンジへ向かった。こういう時、ホテルがそこかしこにあるドバイは便利だよな、と思う。
ドバイの酒は高いので、吝嗇な私は「まあ、一杯だけにしておこう」と考えていた。というか現金の持ち合わせがあまりない。クレジットカードを解約したばかりで、現金だけが頼みの綱なのだ。
しかし、その日はレディース・デイだった。
レディース・デイは、レディーの姿形をしているだけで、お酒が何杯か無料で飲めてしまうという嬉しいシステムのことである。
物価が高いドバイにしては、なかなか慈悲深い・・・と思った人は甘い。
つまりは、女性にドリンクを無料でサービス→女性がたくさんくる→女性との出会いを求めたメンズが押し寄せる→結果的に店の売り上げが上がる、というのが真の狙いである。
と言っても、こうした光景が繰り広げられるのは、ごく一部のクラブやバーぐらいだ。我々がやってきたバーは、最近オープンしたばかりのせいか、人もまばらである。
店は、ラウンジという大人っぽい雰囲気を追求するために、かなり照明を落としていた。窓から見える、ドバイの高層ビル群の夜景の明かりとともに、飲んでもらおうという狙いなのだろう。
しかし、照明を落としすぎたようで、手元にあるメニューすら見えない。店員がスマホの懐中電灯で、メニューを照らす始末である。艶っぽい雰囲気というか、もはや停電中である。
そんなわけで、同僚とともに近況と今後について話あいながら、私は3杯のロゼ・ワインを飲んだ。
どういうわけか、へべれけである。
再び、元自宅へ戻り、荷物をピックアップし、タクシーに乗り込んだ。運ちゃんは、エチオピア出身だった。
最近、どうもアフリカ勢が進出している。
私がやってきた2015年あたりは、タクシーの運ちゃんといえば、パキスタンとかインド出身の人が多かった。
それがどっこい。最近では、アフリカの運ちゃんが増えている。
いや、運ちゃんだけではない。店のショップ店員やホテルスタッフ、観光客に到るまで、アフリカの人が増えているのだ。きっと、ビザ規制が緩和されて、入国や就労がしやすくなったのだろう。
ドバイの街は、ますます競合が激化しているようだ。
「ドバイの暮らしはどうよ?」と運ちゃんが聞いた。
この手の質問をする人は、たいていドバイに対して不満を抱いている。
「俺は、もうドバイなんかうんざりだぜ。何につけても、金だ。さっさと稼いで、国に帰りたいね。万博をやるつっても、もうそろそろドバイは潮時なんじゃねえの」
ドバイをディスりまくっていた数年前の自分を思い出す。ドバイヘイターズの会なんていうのも作ったな。会員は己一人だったけれども。
本来ならば、ドバイの街を感慨深く見つめながら、空港へ着く予定だった。
しかし、終始へべれけだったのと、運ちゃんとのトークに花が咲いたことから、その機会を逃した。
ドバイ空港にやってきて、迎えのレクサスに驚いたドバイ初夜のことを、思い出すこともない。
空港へ入ってしまえば、とにかく素面を装わなければならない。コイツ酔ってる!と見なされると、投獄される恐れもある。それだけは避けたい。
帰りの荷物は、スーツケース2つだけ。やってきた時と、ほぼ同じだ。別途で送った荷物はない。
3キロぐらい重量をオーバーしていたけど、とがめられることはなかった。こういうテキトー感が恋しくなる。
出国もまるで、空気のごとく通過。
最後まで、ドバイらしい夜だった。
ドバイを離れて恋しくなるのは、この多様性だ。
多様性から単一性に特化した国へ帰る私は、そう確信した。