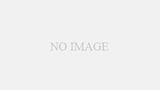2020年2月下旬。東アフリカにある未承認国家ソマリランドでマラソン大会が開かれた。
ソマリランドマラソンは、場所が場所なだけに、一筋縄では行かない場所だった。そんなソマリランドマラソンのレポをお届け。
未承認国家ソマリランドとは?
そもそもソマリランドとは、一体何なのか。
ソマリランドは、世界最恐と言われたソマリアに隣接し、同じソマリ人によって運営されている国でありながらも、ビビるぐらいに治安が良いということで知られる国だ。
一応、国を名乗っているが、世界で認めている国は少ない。よって、未承認国家となっている。日本もソマリランドを国家としては認めておらず、基本的には「あの、危ないソマリアでしょ?」という扱いである。
けれども、ソマリランドの首都ハルゲイサは、一人でも自由に町歩きができるほど、治安が良い。ジモティーですら、ドヤ顔で「どや、ソマリランドは安全やろ」と聞いてもいないのに、アピールしてくる。
日本では空気同然に手に入る安全だが、外国人は護衛つきの車でしか移動できないというソマリアの治安に比べれば、確かにソマリランドの安全は貴重だ。
観光地としての見どころはほぼないが、安全を売りにして、ソマリア感を体験できるというのが、ソマリランドの存在意義である。
そんなソマリランドで、第3回マラソン大会が開かれることになった。2ヶ月前にドバイの会社を辞める時、この大会に出ようと決めた。
決して、走ることが目的だったというわけではない。とりあえず、自由気ままに無職生活を送るよりかは、何か予定が欲しかったのである。よって、この時点では、走ることは大会に出るための、単なる手段でしかなかった。
大会の開催日が決まったのは、大会の1ヶ月前である。昨年は2月9日に開かれたので、おそらくそれぐらいだろうと思っていたら、1月末に「大会の日は2月21日だよん」という発表が流れた。
女が走るのはフツーじゃない
6年前にソマリランドへはすでに訪れたので、治安の面ではさほど心配はしていなかった。が、今回は新たな問題にぶつかった。
それが、女子は走るもんやない!問題である。
前回訪れた時は気づかなかったが、ソマリランドというのは、かなり保守的なイスラーム教の国である。
女性はみな、大きめのヒジャーブをかぶり、髪の毛から体の線をすっぽりと隠している。二カーブと呼ばれる布を顔につけて、目だけしか出していない人もいる。現在のサウジアラビアの女性みたいな感じで、ガチガチにガードしている。
ソマリランドで気がついたのは、そもそも社会において走ることが一般的でない、ということである。ましてや、女性が走ることなど・・・言わずもながである。
大会の数日前に首都ハルゲイサに到着したので、練習がてらホテルの外で走ろうとすると、ホテルのスタッフたちは一様に「ソマリランドで、走るのは、フツーじゃない。やめとけ」などと、ぬかしてくる。特に女性が走ることは、タブーのようであった。
しょうがなしに、ホテルに隣接するジムで走ろうとすると、ジムではそもそも女性が運動することなど想定されていなかった。
どういうことか。
ジムの営業時間は、男女で使用時間帯が分かれていた。このような習慣は、かつてのサウジでもあった。ショッピングモールや博物館では、女性だけが入れる曜日や時間帯などが設けられていたのである。逆にいえば、そのほかの曜日や時間帯には入れないということである。

ソマリランドのジム。経営しているのは、大連に10年近く住んでいたというディアスポラのソマリ人であった。

ジムに飾られていたモ・ファラの写真。ソマリアが生んだオリンピックメダリスト。
それぐらいなら、まだよかった。「女性が使える時間帯はいつなのか?」と聞くと、ジムのスタッフは「朝8時から午後2時ぐらいやで」とのたまう。
くそ暑い時間帯やんけ。
ハルゲイサは標高1,300メートルほどの場所に位置するが、2月であっても日中の気温はぐっと高くなる。
気温30度越えもよくあることで、日差しが強いため日中の間、外に出る人は少ない。人々が活発に動き出すのは、朝の早い時間帯か、夕方過ぎ頃なのである。
そう。つまり運動に適した時間はすべて、メンズの時間帯なのである。
「ジムを使う女なんて、おめえぐらいだよ」と、ホテルのスタッフが言うように、これまでジムを利用する女などいなかったのだろう。
だからこそ、誰もが動きたくない暑い時間帯をしょうがなしに、あてがったのだと見えたる。
ぐぬぬぬ
運動に適した時間帯に、好きに運動もさせてもらえんのか。
このルールを知る前に一度だけ、メンズの使用時間帯にジムへいってしまったことがある。男性2人が使っていたのだが、1人は女が入っても問題ないというのに対し、もう1人は完全にアウトや、というスタンスであった。
見知らぬ未婚の男女が、密室空間にいることは、イスラーム教において好まれない。男女の間にロマンスが生まれて、社会秩序が乱れるからとかいう理由である。
今思えば、しゃーないなと流せるが、当時はかなりフラストレーションがたまった。
正直いうと、今まで親からもさほど干渉を受けたことがない人間にとって、社会の価値観によって、個人のやることが規制される状態は、我慢ならないものだった。
走るぐらい、好きにさせてくれよ。
けれども、ソマリランドでは治安ではなく、社会がそれを許さなかった。
走るという概念がない社会
イスラーム教の国でありながら、そこそこオープンなドバイに戻りたくなった(本当にこの後ドバイに戻る)。
走っても誰にも文句を言われない。ジムだって好きな時に利用できる。そんなドバイが天国に思えてきたのである。
のちに確信するのだが、こうした反ランニング思想はイスラーム教だけが、理由ではない。
発展途上の国では、多くの人は肉体労働に従事している。いや、そうした労働に従事してなくとも、食べ物を手に入れたり、移動するのにずいぶんと体を使うのである。
すでに十分すぎるほど体を動かしている彼らにとって、わざわざ走る必要はどこにもないのである。
それに、体力維持や自己達成感のために走ることを必要とする段階でもない。マズローの欲求5段階で言えば、生理的欲求、安全的欲求の方が優先される社会である。
だからこそ、走る行為はひどく理解し難いものであるし、時には走るものに対して、好戦的な眼差しを向けることもある。
ランニングなんて豊かな国でオフィスワークをやり、時間とお金に余裕がある人間の、優雅なアクティビティにしかすぎないのだ。
そう考えれば、走ることがフツーでない社会において、マラソン大会が開かれるのは、非常に革新的である。
この革新の裏にいたのは、ヨーロッパ系のチャリティ団体だった。私が世話になっているイギリスの旅行会社アンテイムド・ボーダーズもまた協賛企業になっていた。今回のマラソンは個人で参加したので、アンテイムド・ボーダーズにはお世話になっていない。
大会前日に、アンテイムド・ボーダーズの共同設立者ジェームスとばったり遭遇した。イラク旅行ぶりである。イラク旅行では私の勝手な行為によりお叱りを受けたし、もはや2度と会うことはないだろうと思っていたので、ちょっと気まずかった。
この大会の参加費用は200ドル(約2万2,000円)。200ドルといえば、そこそこいいところで焼肉が食べられる値段である。
これは、外国人ランナーの価格。ジモティーランナーの参加費用は1ドルである。外国人ランナーが多く払うことで、ジモティーの参加費用をまかなうという形になっているのだ。一種のチャリティーイベントである。
声援を受け、さっそうと走るはずが・・・
今年で3回目というソマリランドマラソン大会。今年の参加者350人のうち、女性参加者は約100人。女性ランナーは年々増えているのだという。
レースは10キロとフルマラソンのコースがあるが、多くの参加者が出るのは10キロコースである。私が参加したのも10キロである。

会場となったハルゲイサ・スタジアム

スタジアム前のギャラリー。ほとんどがキッズである。

スタートの瞬間を待つ参加者たち。海外からの参加者は全体の1割にも満たない程度だった。

ジモティー女性は、髪の毛を隠すヒジャーブを身につけ、スパッツの上にスカート、そして肌を見せない長袖を着て走る。外国人もみだりに肌を露出させてはいけない。
レースのスタート開始直後、参加者たちは猛ダッシュで走り始めた。通常ならば、ゴール直前でやる全力疾走を、いきなりかまし出したのである。
ひえっ!?
しばらくすると、やはり最初の全力疾走で疲れたらしく、みなとぼとぼと歩き始めた。それから、また体力が回復したようで、走り始めたり、止まったりを繰り返している。どうやら、持続的に走るマラソンという概念がないらしい。
地元参加者の多くは、見るからに10代だった。大人のマラソンというより、中学生のマラソン大会である。
正直いうと、私が思い描いていたのは、アフリカの未承認国家での美しきマラソン大会だった。
「うおおお、よくわからんが、外国人がソマリランドを走ってる〜頑張れ〜」という、ジモティーの声援を受けながらさっそうと走る、というのが私のイメージだった。
が!
現実は甘くなかった。
とんできたのは、黄色い声援ではなく「チャイナ!」「チャイナじゃね?」「チャイナが走ってる、ウケる〜」という野次だった。
「いいぞ〜頑張れ〜!」と、まともに声をかけてくれたのは、大会運営に携わるヨーロッパ人のみであった。
我々にとって、マラソンと応援というのはセットである。いや、とにかくスポーツしている人がいたら、応援するという流れがある。
けれども、スポーツをすることが一般的ではない社会においては、スポーツをしている人を応援するなんて発想はないのだ。
外国人だからアウェーということではない。地元のソマリランド人ですら、沿道の人々から応援されていないのである。
こうして私は、最初から最後までひたすらチャイナコールを受けながら、走るはめになった。
さらに、走っている人間が珍しいのか、その辺にいたキッズが大量に乱入し、並走してくるのである。
また、参加者のヤングがそれまで歩いていたのに、私が近づくと急に対抗心をあらわにして、「抜かされるもんか!」と、ぴったりと並走してきたり。折り返し地点で、全速力で走りながらハイタッチをかましてくるソマリヤングなど。
ひええええ
なんというか、ソマリ人は荒々しい。
若さゆえなのかもしれない。
いろんな意味で疲れたマラソン大会であった。この際、タイムなどもうどうでもよかったのだが、1時間1分33秒で自己新記録を更新していた。これが、唯一の救いである。

完走者に送られるメダル

大会終わりには、ドリンクやスイカ、ビスケットなどが配られた。食べかすや飲み干したペットボトルは、無残にもその辺にポイ捨てされている。

ジモティー参加者が集まってきたので、記念撮影。体つきからしてソマリ人というのは、走るポテンシャルがありそうだが・・・

テレビ取材を受ける筆者。外国人も髪の毛を隠したり、肌を隠さなければいけないため、このような格好になっている。いかにも清清しく走ったような顔をしているが、テレビカメラの前なので取り繕っているだけである。本当は荒々しいソマリ人たちに疲れている。
ここにやってくるまで、サウジアラビア、エチオピア、ソマリランドと旅をしながら、走り続けた。
それは、単に走る練習ではなく、社会のあり方について考える時間でもあった。走ることは、日常生活の一部なのだと思う。
旅という非日常の中にいながら、走ることでその社会の日常に触れる。私にとって走る意味は、そこにあったのかもしれない。
ソマリランドで驚いたのは、保守的なイスラームのあり方である。ソマリランドの女子ランナーは、ヒジャーブをかぶり、スパッツにスカート、長袖という出で立ち。なるべく軽装で、という我々の運動スタイルとは真逆だ。
実際に女性ランナーが走っているときに、「なんで女子が走る必要があるんや。家におったらええのに」という野次も飛んできたという。
これが私が聞いたわけではなく、NYタイムズが報じたところによる。NYタイムズが、ソマリランドマラソンを取り上げるのも驚きだが・・・
ソマリランドは、女性が自由に運動できる環境が整っているわけではない。フルマラソンでも、地元の男性ランナーはいたが、女性部門で参加したのは外国人選手だけだった。
それでもこうした逆境の中、青少年たちが町中で走り始めたことは、社会にとって変化の一歩なのだろう。ソマリランドで走ることは、他の先進国で走ることよりも、ずっと大きな意味を持つのだ。