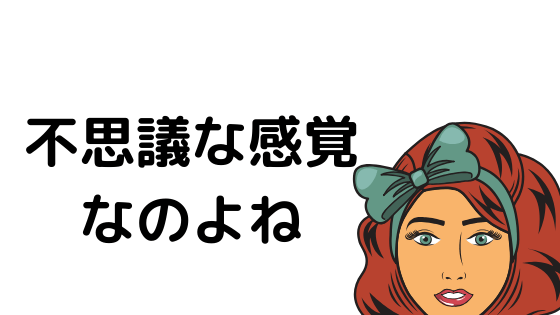ヨルダン滞在中に、ひょんなことからシリア難民キャンプを訪れることになった。
そのことを記事にまとめたのだが、かなり長くなってしまった。
シンプルに短く、というのが今や物事を伝える上での常識だろう。
でも、あえてここでは長文にしている。さっさと結論だけをいわんかい、と思われるかもしれない。
けれども、状況やバックグラウンドが日本とまったく異なり、複雑な事柄になるほど、補足も含め伝えるべきことは多くなる。
情報をそぎ落として、シンプルにしたところで、伝わらないことも多々あると思う。だから、長文のままである。時間にすれば、山手線で渋谷から新宿に行くぐらいだが、引き返すなら今のうちである。
非公式の難民キャンプ
現在ヨルダンには、67万人のシリア難民がいる。といっても、こうした難民がすべて難民キャンプに暮らしているわけではない。
UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)によれば、ヨルダンでは85%の難民が難民キャンプ以外の場所で生活しているのだという。
ヨルダンのシリア難民キャンプと言えば、シリア国境から15キロの場所にあるザアタリ難民キャンプがよく知られている。シリア難民キャンプとしては世界最大。
そのほかにも、アズラック難民キャンプなど、ヨルダン国内にはいくつかのキャンプが存在する。
ヨルダンに住む人間いわく、これらは公式の難民キャンプなのだという。それに対し、地元の人々が”非公式”と呼ぶ難民キャンプもある。
公式の難民キャンプは、特別な許可がないと入れない。よって、私が今回訪れたのは、非公式の難民キャンプである。非公式であり、かつ規模は大きくないため、正式なキャンプ名というのはない。
ヨルダンに住む知人のシリア人ララが、難民キャンプに物資を届ける、というのでそれに同行したのだ。
ララは、2012年にシリアの首都ダマスカスから、ヨルダンへ逃れてきた。
本人いわく、当時はたった数ヶ月で故郷に戻れると思っていたらしいが、それがいまや7年にもなる。現在は、ヨルダンで会社を立ち上げ、シリアの難民女性をサポートする会社を運営している。
会社の運営とは別に、ヨルダン国内にあるいくつかの非公式難民キャンプを、個人で定期的に回っているのだという。
難民への差し入れ
キャンプへ同行する前日。手ぶらなのも何なので、差し入れは必要か、とララに聞く。
難民キャンプに行くときには、差し入れを持って行くというマナーはないが、今回は物資を支給する、という目的だったので聞いたのである。
犠牲祭の時期でもあったので、ララは冷凍した肉を大量に持って行くのだという。
ララ:「そうねえ・・・他に必要なのは、アバヤ(アラブ女性の民族衣装。長袖ロングスカートみたいなもん)かしら。シリア人女性が作っているアバヤを買い取って、持って行こうと思うんだけど。アンタ、どれぐらい買い取れる?ちなみにアバヤは1着10JD(約1,500円)ね。」
私:「何着ぐらい必要なのかにもよるけど・・・20着とか・・?」
ララ:「OK。じゃあ、アンタは20着でいいわ。アタシのほうで10着分買い取って持って行くし」
私:(30着以上必要ってこと?)「待て待て。なら、こっちで50着買い取るわい」
ダチョウ倶楽部みたいなやりとりになってしまった。
ララの友人、リーンが途中で合流し、我々はアンマン市内から空港方面に車を走らせた。到着したのは、市内から車で30分ほどの場所にある、農業地帯だった。
あたりに民家らしい民家はなく、農業用のビニールハウスや、掘建小屋のようなものが、ポツポツと並んでいる。
アンチャッチャブルな世界
リーンは、現在ヨルダンの大学院で、薬学の勉強をしている。彼女もまたダマスカス出身。2012年の10月に、家族とともにヨルダンへやってきたのだという。
私:「なんでまたヨルダンへ?」
リーン:「私の叔父が誘拐されて、1,000万シリアポンド(約200万円)の身代金を要求されたの。もちろんすぐに全額は用意できなかったから、一部を支払って叔父は解放。だけど、全額払わなかったら、家族の誰かをまた誘拐するって脅されてさあ。それで、シリアを離れたワケ」
リーン:「まあ、シリアではよくあることなんだけどね」
誘拐がよくある・・・?
内戦とかいう以前に、シリアは相当ヤバい国なんじゃないかと最近では思う。なんというか、人々が恐怖政治に支配されているというか。
同僚のシリア人と話しているとよく思うのだ。彼もまた、米軍の空爆で家がヤバくなった(本人いわく)からドバイに逃げてきたという人物である。
ドバイであっても、政治の話をする時は、あたりをキョロキョロと見回して、ヒソヒソ声で話す。人に聞かれたくないというより、聞かれたらとんでもないことになる、という恐怖がうっすらとにじみでているのだ。
はたから見れば、何をそんなにビビっているんだ?と思うが、彼には一種の恐怖が染みついているようだった。
シリアでの思い出を語っていた時も、親しい友人が反政府的な言動をとったため、どこかへ連れ去れらたなどいう話も聞いた。
そこには言論の自由が制限され、為政者の陰口を叩こうものなら、すぐさま逮捕、拷問という世界が当たり前に存在するようだった。
平和な国に住む我々からすれば、映画のような世界である。
話を戻そう。
足りない物資
車を降りると、「待ってましたあ!」と言わんばかりに、物資の到着を待ち構えていた大量の人々が押し寄せてくる。
挨拶もそこそこに、さっそく物資の配給が始まる。

配給に押し寄せる人々
「アナタの家族は、女性が何人いるの?3人?じゃあ、アバヤ3つあげて」と手際がいいリーンに指示されるがままに、私はアバヤの配給係りを担当することになった。
リーンは、肉担当である。私の横でせっせと、ビニール袋に入ったサイコロ状の冷凍肉を手渡している。
配給はものの10分ほどで終わっただろうか。物資がなくなったとわかると、蜘蛛の子を散らしたように、人々はどこかへ去って行った。「お前らにもう用はねえ!」と言わんばかりである。
一方で「物資もらってないんですけど?」と、残留する人々もいる。

まだお肉とアバヤもらってませんけど・・・
全員に行き渡ってないじゃあん?
ということで、ララ、リーン、キャンプの代表者を含めて、緊急会議が催された。

仮設テント内にて。右側の男性がキャンプ代表
何度かこのキャンプに物資を運んでいるララやリーンにとっても、想定外だったらしい。
ララ:「ちょっとお。電話では20~30人程度っていったじゃあない。どういうこと?」
キャンプ代表:「いやあ、それがアンタらが来ることが、別の家族にも伝わっちゃって、想定以上の人間が押し寄せちゃったんだよな」
ここはキャンプといっても、いろんな人間がひしめくように住んでいるわけではない。むしろ、1~3家族で形成されるグループが、一定の距離を置いて各々の敷地に住んでいるといった感じである。
なるほど、こういうところが”非公式”っぽい。おそらく公式のキャンプであれば、国連などが、どこに誰が何人住んでいるかをきちんと把握しており、配給の管理も行き届いているのだろう。
都会と地方という意識
目の前にいる家族グループは、シリアで内戦が始まった2011年に、シリア中部のハマという都市からヨルダンへ逃れてきた。
ハマは、ホムスからたった40キロの距離だ。ホムスは、その戦闘の激しさから日本のメディアでも何度も取り上げられた場所だ。
彼らが国を離れたきっかけは、「ある日突然、家が壊されたから」だという。
「このキャンプに住む人は、学がないのよ。この人たちには、反政府側も政府軍もわからない。ただ、自分の家がなくなった。危険だ、じゃあ、国を出ようという短絡的な思考なの」と、ララが補足した。
結構なディスりようである。
同行したララやリーンは、シリアの首都ダマスカス出身。ハマもシリアでは一応5番目に大きい都市ではある。日本で言えば、福岡的な存在である。
しかし、そこには東京に住む人間が、地方の人間をみやるような、都会VS地方という構造が存在しているらしかった。
「最近では国連の支援も少なくなってきて。数年前は、子どもを産む時に出産費用として800JDを支給してくれたんだ。でもいまじゃあ、ほぼ全額自己負担だからな」
私は、純粋に思った。
この状況ならば、子作りやめようなどと思わないのか?
世界的に見れば裕福なレベルの日本人でさえ、「金がないから結婚できない。子どもを産めない」とぼやくのだ。
直接本人に聞くのははばられたので、隣にいたララやリーンにたずねてみた。
リーン:「子作りは、彼らにとってエンターテイメントなのよ」
は?
ララ:「彼らはそれすらも考えられないの。それに、この家には何もないでしょ。夜になったら、何もすることがなくて、寝るしかないのよ。要は娯楽がなくて暇なの。だから、子作りするの」
なるほど。
そして私は真面目に思った。次回来る時は、性教育、避妊方法、コンドームなども差し入れようと。
おしゃれタトゥー
さっきから気になることがある。不思議な文様を顔に刻んだばあさんがいるのだ。

額になにやら文様がついているばあさん(左)
耐えきれなくなって、「顔の文様はなんですか」とたずねた。
ばあさん:「ああ、これはねえ。タトゥーなんだよ。昔はこのタトゥーが美しいと思われてたんだよ」
まさかのおしゃれタトゥー!?
しかし、顔面にタトゥーをするとは、結構な度胸である。

いかつい感じのタトゥーを入れたばあさん(左)
のちに調べてみたところ、トルコ南部やシリアの一部では「デク」と呼ばれる伝統的なものらしい。専門家によれば、所属している部族を示したり、模様にもそれぞれ意味があるのだという。
難民でも家賃と光熱費は払う
果たして、彼らはいかなる暮らしを送っているのだろうか。
聞けば、働くのは男だけで、女たちはもっぱら専業主婦をつとめているらしい。
家にずっといても暇じゃね?料理をするにしても、すぐおわっちゃうじゃん?
「ここでは、料理もそんなに簡単にできるもんじゃないの。いろいろと手間暇がかかるのよ。料理をするのにも、時間がかかるんだから」と呆れ顔で、ララとリーンに諭された。

キッチン。敷地内に別個の仮設テントが連なっており、それぞれのテントがキッチンだったり、お風呂場になっている。
そうか。料理の時間などもったいない。削減してなんぼやという、1人暮らしの生活とはまるで違うのだ。
働くにしても、大きな制限がある。ここに住む彼らは、主に農作業の仕事をしている。
仕事はあっても、ここでは、1日に2~3時間程度しか働けないのだという。時給は1JD。日本円で約150円だ。仕事も定期的にあるわけではない。
シリア難民では、正規の労働契約を結べない。ヨルダン政府は、シリア人難民に対して就労許可証を発行しているが、数は限定的だ。誰もが簡単に働けるわけではなさそうだ。
しかも、最近では仕事ができる農業系エジプト人が流入しているという。
よって、雇う側からすれば、スキルがあり、契約書を交わせるエジプト人に働いてもらいたいのである。といっても、エジプト人の時給もそれほど変わらない。
単純労働でも、今や奪い合いなのだ。
ざっと、目の前の家族を見るに子どもは、3~5人ぐらいいる。当然、男の稼ぎでは、みなを養うことができない。
彼らは、国際機関から、食料クーポンを毎月受け取っている。家族が6人以上であれば、1人当たり毎月15JD(約2,200円)。6人未満であれば10JD(約1,500円)である。
仮に5人家族で、男がフルに働いたとしても、月の収入は100JD(約1万5,000円)以下だ。こうした状況下でも、家賃と光熱費を払わなければいけない。
こんな仮設キャンプで家賃をとるのか?
よく聞けば、土地に対して年間で900JD(約13万円)の借地料が発生するのだという。借地料は、複数の家族グループで共同負担している。
一見すると、価値のなさそうなどうでもよい土地に対して、難民から土地代を請求するという地主の神経は、どうかしてる。無慈悲だ。

こんな土地でも家賃は発生する
さらに、テレビや冷蔵庫などもあるせいで、光熱費も払わなければいけない。月にしておおよそ15JDである。
肝心の子どもの教育。現時点で、子どもたちは、ユニセフが運営する学校へ通っている。給付金として、こどもたちは月に20JDほど受け取っているらしい。
しかし、食料クーポンにしろ、ユニセフからの給付金にしろ、年々給付額は減っているとのこと。
いつ支援が途絶えるのか。それが一番の懸念、だという。
難民はみな不幸なのか
テント内は清潔感もあり、テレビもあった。形だけは風呂もトイレ(野外トイレだが)もある。お風呂場には洗濯機もあり、キッチンには調味料は一式そろっているらしかった。

洗濯機がついたお風呂場。ためた水を蛇口から出して、体を洗う

青空トイレ

トイレ内。大をした時の処理法が若干気になる
正直、暮らしぶりを見る限りでは、そこまで悪くない、と私は思った。
なんて発言をすると、「そうじゃないのよ!」とリーンが若干キレだした。
ひえっ!?
「確かにねえ。テレビも冷蔵庫もあるかもしれない。でもあれは、すべて寄付されたものなの。彼らは、パンすら買えないんだってつぶやいていたのよ」
「この時代に、携帯すら持ってなくて、ネットにだってつながっていないのよ。そんな生活がいいわけないでしょう」
まあ、確かに我々の暮らしからすれば、彼らの生活はないものだらけである。見ようによっては、それは悲しいことなのかもしれない。
でも、私からすれば、よく見かける生活風景なのである。
貧しく、先進的ではない暮らし。ソマリアやイエメンのソコトラ島、イランのゲシュム島。あの手の生活形態は、こうした場所でもよく見るものなのだ。
本人たちが、自分たちは貧しくて、不幸なのだという自覚があるのかはともかく、それほど深刻そうに暮らしているわけではない。
はたからみると「パンが買えないんだよお」という難民の顔の方が、豊かな国で「マジ、死にてえ」と、うつうつとする人間よりも、生き生きしている。少なくとも私にはそう思えた。
何が不幸で、何が幸せなのかは、本人が感じることなのだ。他人が客観的に判断できるものではない。
なぜ支援を続けるのか
キャンプからの帰り道。私は不思議に思っていたことを、ララに聞いた。
なぜ、彼らを支援し続けるのか、と。
アンマン市内のアパートで暮らしている彼女も、一応はシリア難民だ。
別に彼女は、仕事を斡旋したり、定期的に物資を運びつづけているわけではない。
あくまで、個人として年に数回、ポケットマネーで物資を購入し、彼らに届けているだけだ。
なぜ、身銭を削ってまでも、「学がない」とディスる人々を支援するのだろうか。イスラーム教の教えゆえなのだろうか。
「今はねえ、100万人以上のシリア人の子どもが難民だといわれているの。100万人よ。もし、彼らを見捨ててしまえば、失われた世代になってしまう。彼らを支援することは、私自身と、そしてシリア人の未来のためでもあるの」
はっとした。
現時点での利益ばかりを考えて、物資支援は根本的な解決などになりはしないと、絶望している人間には、決して思いもよらないことだった。
自己本位な自分を見透かされたような気がして、さびしかった。